子宮内膜症と子宮内膜炎の違いとは
ずっと以前から体質的な問題として知られる「子宮内膜症」と、不妊治療が活発になり注目されてきた「子宮内膜炎」。
不妊治療の場ではそれぞれ”別のもの”として扱われるかもしれませんが、呼び名は似ていますが、漢方的な理解は”少し”違います。
子宮内膜症は、本来子宮の内側にだけ存在するはずの子宮内膜組織が、子宮の外にも増殖してしまう病気です。
主な症状としては、強い生理痛、排便痛や性交痛などで、卵管の癒着や卵巣機能の低下の要因となる場合もあり、不妊治療を受ける女性の約30~50%に子宮内膜症が見られるともいわれ、不妊に関連する重要なトラブルのひとつとなります。
① 卵管の癒着・閉塞による受精障害
卵巣や卵管が癒着することがあり、排卵やピックアップや受精を妨げ、卵子がスムーズに移動できず、自然妊娠が難しくなる場合があります。
② 卵巣機能の低下
子宮内膜症が卵巣に発生すると「チョコレート嚢胞」と呼ばれる古い血液が溜まった嚢胞(のうほう)が生じ、卵巣の働きを妨げ排卵がうまくいかなく場合があります。
③ 着床障害
子宮内膜の質が低下し、受精卵が着床しにくくなることがあります。
悪化や癒着がひどく、スムーズな妊娠を妨げる要因となっている場合は、ピルや黄体ホルモン剤により一時的に生理を止めることで、悪化を防ぐ治療が行なわれますが、ホルモン療法中は妊娠できなくなります。
また、妊娠率向上を目的に腹腔鏡手術で病変を取り除く治療では、卵巣の手術をした場合に卵巣機能が低下するリスクもあります。
子宮内膜症が発生する原因やメカニズムについて、西洋医学でははっきりとした原因は不明ですが、経血が卵管を通じて逆流し、腹腔内に定着する説(逆流月経説)が有力視されており、ホルモンバランスの乱れや免疫機能の異常も関与していると考えられています。
一方、子宮内膜炎は、細菌感染が原因で子宮内膜に炎症が生じる疾患で、急性と慢性の2種類があり、不妊治療の場で不妊との関連が深いとされるのは慢性子宮内膜炎です。
慢性子宮内膜炎では、自覚症状はほとんどなく不妊女性の約30%、特に着床不全(何度も移植しても妊娠に至らない)や習慣性流産の既往がある場合では割合が高いようです。
不妊治療への影響としては、子宮内膜に炎症があることで受精卵が着床しにくくなり、受精卵が着床したとしても炎症が続いていると子宮内膜の質が良くないため、妊娠の維持が難しくなり流産しやすくなります。
また、ホルモン剤に対する反応が悪くなり、子宮内膜が十分な厚さに形成されにくいとも考えられます。
原因は、子宮内に大腸菌やクラミジア、淋菌などの細菌が侵入し、炎症を引き起こすとされ、出産後や流産後、子宮内手術(掻爬〈そうは〉手術・人工妊娠中絶など)を受けた後にリスクが高まります。
不妊治療において慢性子宮内膜炎の検査は保険適用外で、費用は自己負担となります。
EMMA(子宮内膜マイクロバイオーム検査)やALICE(感染性慢性子宮内膜炎検査)などの先進医療として認定されている検査については、混合診療が可能とされていますが、ERA(子宮内膜着床能検査)や子宮内フローラ検査なども特殊検査として各医療機関で自費診療として提供されています。
漢方では、病院で行うような検査はありませんが、子宮内膜症も子宮内膜炎も「瘀血(おけつ)」に含まれるととらえます。炎症や痛みは血流の滞りによると考えられます。
一陽館薬局では、子宮内膜症も子宮内膜炎も根底に「瘀血」という体質的問題があるという観点から、お一人おひとりの状況に応じて最適な漢方処方をご提案し、妊娠に向けての体づくりをサポートしています。
検査は西洋医学、体質の改善は漢方とうまく利用するのも、ひとつの方法ですね。

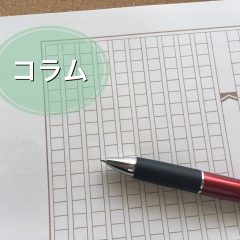






この記事へのコメントはありません。