卵はあるのに妊娠しづらい〜多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)〜
「卵がたくさんあるのに、なぜ妊娠しづらいの?」とご質問いただくことがあります。
「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」と診断され、不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)とは、卵巣の中で小さな卵胞がたくさん育つのに、排卵まで進みにくい状態を指します。
卵が途中まで育っても停滞してしまって成熟にいたらず、排卵がスムーズに起こりにくくなるのです。
医学的な検査では、ホルモンのアンバランスが確認されます。
FSH(卵胞刺激ホルモン)が働きにくく、LH(黄体形成ホルモン)が相対的に高くなりやすいことに加え、インスリン抵抗性(血糖をうまく処理できない状態)が影響することもあり、代謝や生活習慣とも深く関係しているといわれます。
どうして多嚢胞性卵巣症候群があると”妊娠しづらさ”につながるかを考えてみます。
排卵がスムーズに起こらないため、生理周期も長引きがちとなり、一定期間内での排卵(チャンス)回数自体が少なくなってしまいます。
また、周期も不順であるため排卵のタイミングがつかみにくく効率よく妊娠するこのが難しくなってしまう可能性もあります。
卵子の成熟が停滞することから子宮内膜の状態が安定しにくく、着床に不利となってしまいます。
ベースにホルモンバランスや代謝の乱れが影響するものであり、妊娠を迎える体内環境そのものを整える必要もあります。
つまり、妊娠に必要な「卵の成熟」「排卵」「着床準備」の流れが滞り必要な条件が整いづらいのです。
PCOSになる原因は解明されていませんが、いくつかの要因が関わると考えられています。
・遺伝的な体質=家族に月経不順やPCOSがある場合
・インスリン抵抗性=血糖値の乱れがホルモン分泌にも影響
・生活習慣=食生活の乱れや運動不足、睡眠リズムの乱れなどによるホルモンバランスの乱れ
体質的要因を漢方で見てみると、おもに「痰湿(余分な水分や代謝の滞り)」「瘀血(血流の滞り)」「腎虚(生殖力の不足)」などが関係していると考えられており、「ため込み・停滞」タイプの方は要注意です。
糖質中心の食事を避け、たんぱく質や野菜をしっかりとること、軽い運動や筋トレで代謝をよくすること、睡眠を整えてホルモンのリズムを安定させることなど、日々の小さな積み重ねでホルモンバランスは整い始めるのではないでしょうか。
PCOSは卵巣に卵はある、どちらかと言えば多めにあるわけで、排卵誘発剤などの刺激もなかなか効果的でない、時に過剰刺激傾向になってしまう場合もあり、できれば内面から「気血水バランス」を整え、自然にあるべきリズムで排卵することをめざしたいですね。
妊娠への体づくりに近道はないかもしれません。
でもあなたにとっての最短ルートはあるはずです。
※ブログで取り上げて欲しいテーマはInstagramDMまたは公式LINEメッセージにて受付中
◎陽子先生妊活Instagram

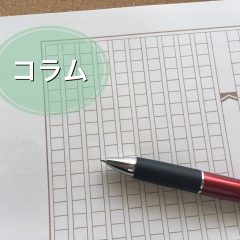






この記事へのコメントはありません。